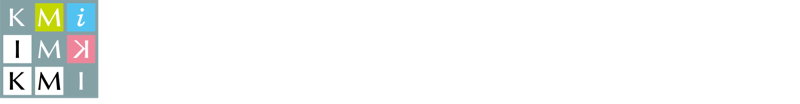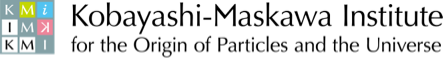奇核の構造:密度汎関数理論が挑む未踏の世界 — なぜ難しいのか?何が面白いのか?
Closed
KMI Seminars
2025-08-29 14:30
吉田 賢市/大阪大学核物理研究センター
ES635
Iビーム技術の進展により,従来は安定同位体に限られていた原子核研究は,中性子数や陽子数を広く変化させた不安定核へと大きく拡がってきた。これに伴い,理論的にも広範な質量数領域を統一的に記述できる枠組みの構築が求められている。
現在,その有力候補として注目されているのが原子核エネルギー密度汎関数(EDF)法である。原子核EDF法は,密度の変分原理に基づいて基底状態のエネルギーや密度分布を与える密度汎関数理論を原子核系に応用したものであるが,そのモデル化には多くの課題が残されている。また,これまでの原子核EDF法の多くは偶々核(陽子数・中性子数がともに偶数)を中心に発展してきた。
奇数個の核子からなる核(奇核)や陽子数と中性子数が共に奇数の核(奇々核)は基底状態でも一般に有限の核スピンをもつが,偶々核の基底状態の核スピンは例外なくゼロである。このような原子核における偶奇の差は主に,原子核中で同種2核子が合成スピンゼロのペアを組む,スピン一重項対相関の結果として生じる。対相関による核子対の凝縮は,電子系と同様,原子核に超伝導・超流動性をもたらすが,奇核や奇々核では対を組まない“余分”な核子が存在することが特徴的である。本講演では,我々が提案した「ある種の外場の下での変分原理」[1] を通して,余分な核子が持つスピンをどのように理論的に扱うのかを概説する。また,奇核の構造が,原子核EDFそのもののモデル化にどのようなインパクトを与えるのかについても議論する。
[1] H. Kasuya and K. Yoshida, PTEP 2021, 013D01 (2021).