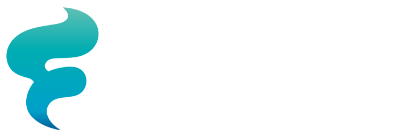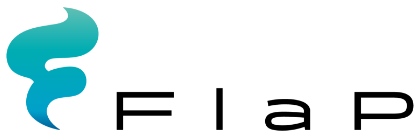FlaPが目指すもの
フレーバー物理学国際研究センター(FlaP)は、素粒子標準模型の検証およびそれを超える新物理の発見を目指して、フレーバー物理に関する国際的な研究・教育を推進します。Bファクトリーにおけるボトムクォークとタウレプトンに関する研究、LHCアトラス実験におけるトップクォークとヒッグス粒子に関する研究を発展させるとともに、J-PARC等の施設におけるミューオンやニュートリノの研究を加えて、包括的、多角的な素粒子研究を進めます。先進的な測定装置の開発、最先端データサイエンスを導入したデータ解析により、プロジェクトを主導し成果を得ていくことで、地球規模の国際共同研究における名古屋大学のプレゼンスを高めます。

研究体制
FlaPは、名古屋大学の素粒子宇宙起源研究所に設置されたセンターで、
ヒッグス物理部、クォーク物理部、レプトン物理部で構成されます。
クォーク物理部
クォーク物理部では、茨城県つくば市のKEK(高エネルギー加速器研究機構)における電子・陽電子衝突型加速器を使ったBファクトリー実験におけるボトムクォークとタウレプトンの研究を行います。
レプトン物理部
レプトン物理部では、茨城県東海村のJ-PARC(大強度陽子加速器施設)におけるミューオンとニュートリノの研究を行います。
ヒッグス物理部
ヒッグス物理部では、スイスのCERN(欧州原子核研究機構)にある大型陽子衝突型加速器LHCを使ったアトラス実験におけるトップクォークとヒッグス粒子に関する研究を行います。
また、学内外との連携のもと、名古屋大学における国際共同研究推進の拠点として、
様々なプロジェクトを推進します。

フレーバー物理学とは
フレーバー物理学は、クォークとレプトンの素粒子反応の測定を通じて、その背後に存在する基礎的な物理法則を見出す学問です。フレーバーには「香り」の意味がありますが、素粒子物理学においては、クォークとレプトンの「種類」を指します。これまでに、クォークが6種類、レプトンが6種類あることが観測されており、それぞれ質量と相互作用などが異なります。 2012年には、スイス・フランス国境付近に設置された加速器「LHC」を用いて、ヒッグス粒子が発見されました。ヒッグス粒子は、フレーバーを特徴づける質量の起源を担うと考えられています。ヒッグス粒子の研究により、フレーバーの理解が進展し、より本質的な素粒子像に迫ることができます。

フレーバー物理学と名古屋大学
名古屋大学は、小林・益川理論検証の舞台となったBファクトリー実験におけるボトムクォーク物理とタウレプトン物理、LHCアトラス実験におけるトップクォーク物理など、大型国際共同研究の中で独自性の高い研究を展開し、多くの博士人材を育成してきました。フレーバー物理学研究センター(FlaP)を設置することで、これらの研究を格段に発展させ、消えた反物質の謎の解明などの現代素粒子物理学の課題に挑戦していきます。